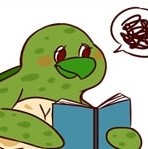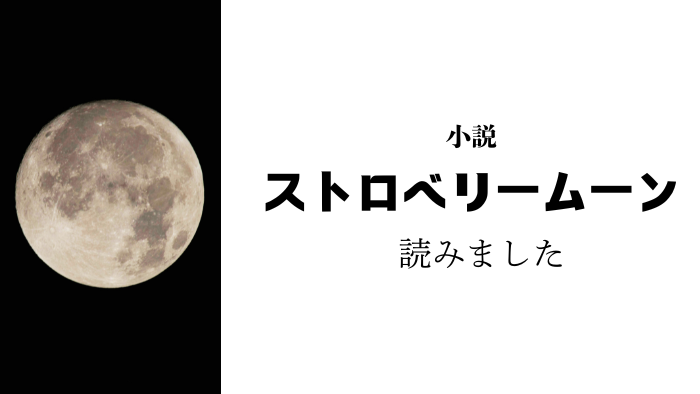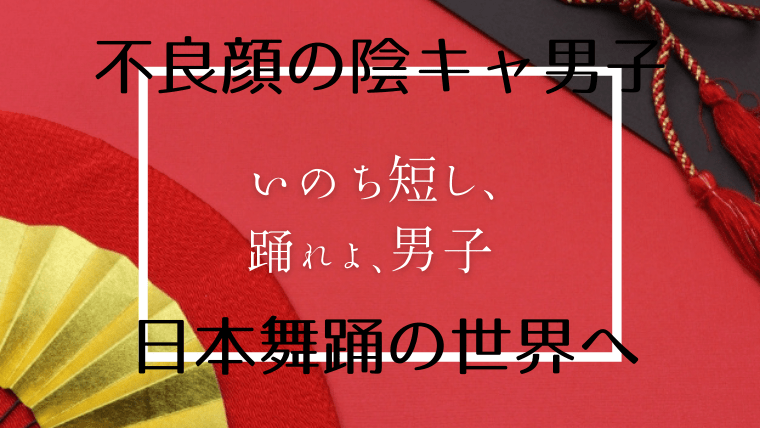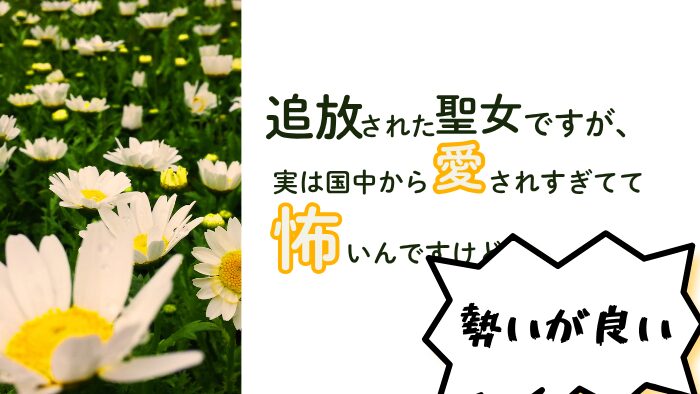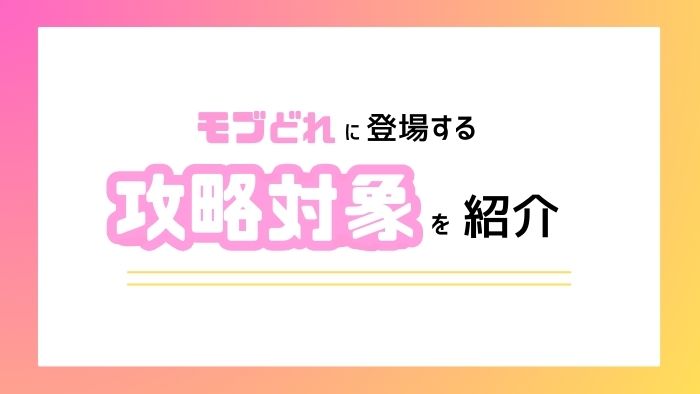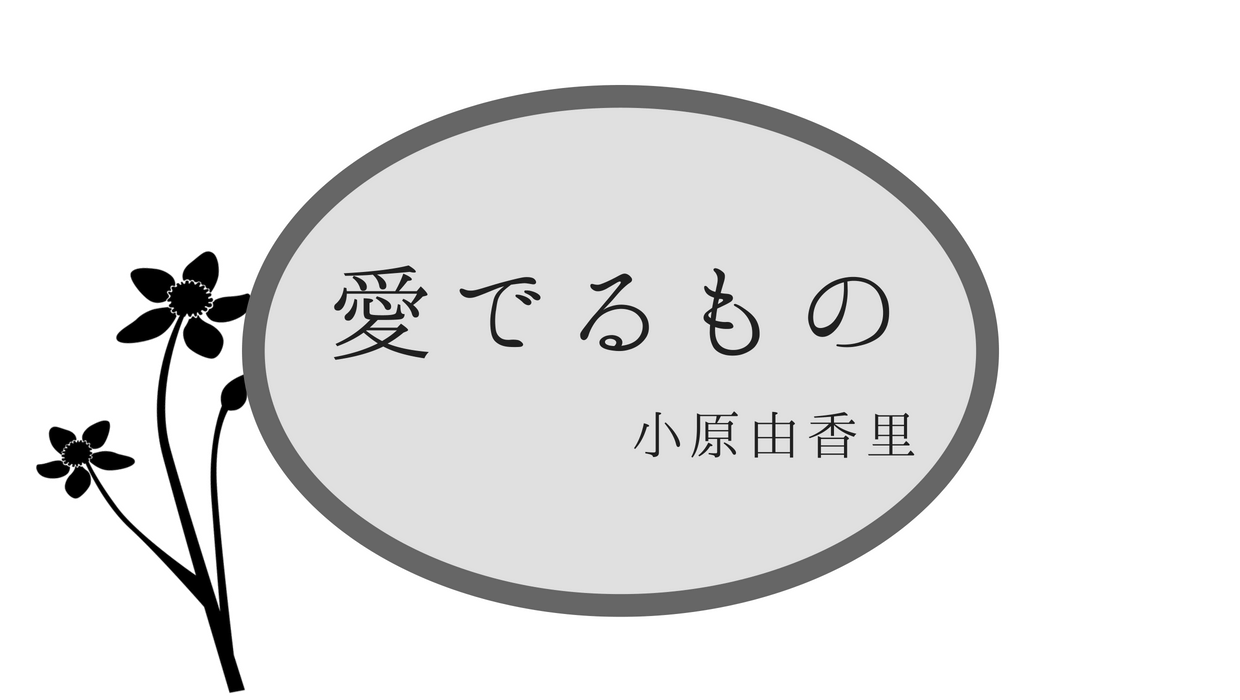時計じかけのオレンジを観ました

スタンリー・キューブリック監督の「時計じかけのオレンジ」を観ました。
以上です。
……いや、もう何を言えばいいの?
何を言えばいいのかわからないんですけど、衝撃は大きかったです。
感想としてまとめねばという気持ちが湧いたのは確かなので、書きます。
時計じかけのオレンジについて知っていたこと
「シャイニング」と監督が同じだってことは知っていました。
同監督による「シャイニング」は昔から観ていまして、こちらは好きでした。
ホラーは得意じゃないけど、「シャイニング」は観られます
「時計じかけのオレンジ」は、なんかやばいらしいと聞いてはいました。
この映画に関する情報はふんわりとしか持っていません。
タイトルを耳にする度に気になって簡単なあらすじだけは調べていたような覚えはあります。
ですが、内容をほとんど記憶に留められずにいました。
そんな状態で、ふと「そろそろ観てみるか」と思い至って視聴してみた形です。
思っていた通りやばかったと言いますか、思っていた以上にやばかったと言いますか……
「暴力」「性暴力」といったことが多い(多いというかほぼそれ)映画です。
多いどころかほとんどがこれで構成されています
こういうのが無理だって言う人は観ない方がいいです。絶対に。
私はかなり、こう、きつかったです
どんな映画か答えづらい映画
どういう映画だったのか、と訊かれたら回答にものすごく困ります。
わかったのは、この映画が一種の芸術であることと、視聴した人の好き嫌いが極端に分かれるタイプの作品であることです。
一種の芸術
表現しづらいのですが、観終わった後の胸に浮き出てきたのは「これは恐らく、ある種の芸術なのだろう」という思いでした。
芸術だろうと思ってはいるのですが、その芸術性を私では理解できないかもしれない、という感覚があります。
でも、これだけは確信に似た思いを抱いています。
この映画は、刺さる人にはすごく刺さる映画だ、という直感です。
好き嫌いが極端に分かれそうな作品
星1の評価をつける人と星5をつける人が合わさって、平均化されて星3くらいの評価が出てきそうな映画だ、と感じています。
実際、後で評価を調べてみたらそんな感じでした
[ac-box01 title=”「刺さる人には刺さる」と感じた理由”]正直に申し上げますと、私はこの映画は苦手です。結構、苦手です。
私は、「私の好きは誰かの嫌い、誰かの嫌いは私の好き」という考えを持っています。
どこかで聞いた話の受け売りではあるのですが。
とにもかくにも、私が強烈に「苦手」と感じたということは、どこかにこの作品を熱烈に惚れ込む人もいるのだろう、と考えられます。
そんなわけで、「時計じかけのオレンジ」のタイトルが今なお語り継がれていることも踏まえて、「刺さる人にはしっかり刺さる映画だ」と判断したのでした。[/ac-box01]
独特なスラングが多用されている
私は字幕で観ました。
どうやら吹き替えは存在していないようです。
吹き替えが作られなかった理由もわかるような気がしました。
この映画では、字幕にめちゃくちゃ下線が引かれています。
映画を何百本と観ている、というわけでもないのですが、下線つきの字幕は初めてでした
後で調べたところ、ナッドサット語という、独自の言葉だったようです。
「スパチカ」とか「マレンスキー」とか、さっぱりわからない言葉がどんどん出て来ます。
この映画の持ち味を維持しつつ吹き替えを作るのは至難の業でしょう。また、その必要もなさそうなくらい、映画が力強いです。
出てくる独自言語はさっぱり知らないものばかりなのに、ずっと観ているとなぜか何となく意味がわかってくるようになります。
不思議な体験です
はじめのうちは「観づらいなー」と思っていたのに、映画の中盤頃には、下線ばかりの字幕も気にならなくなりました。
ちなみに、言語の意味はこちらのサイトが参考になりました。
【台詞・言葉】『時計じかけのオレンジ』に登場したナッドサット言葉をまとめた「ナッドサット言葉辞典」(KUBRICK.blog.jp)
視聴後にこちらで確認して「なるほど?」とか言ってました
舞台で踊るような
色々と言語化しがたいものが多い本ではありました。
しかしながら、印象に残ったシーンもあります。
印象に残るシーンしかないような映画なので、この表現はあまり適切ではないかもしれませんが……
特に印象に残っているのは、主演のマルコム・マクダウェルの仕草です。
ちょっとしたときの動きが芝居がかっているようでした。
ちょっとした動きというのはポケットから所持品を出して机に置くときの腕の動きや、気をつけをして直立するときの足の動きといったものです。
物を出すだけなら、ポケットに手を入れてペッと出してしまえばいいのに、わざわざ腕を大回りさせてから、すっと机に置きます。
このときの腕の動きが美しいし、同時に嫌味っぽくも見えて好きです。
足の動きも同様でした。
隣を歩いている人は四角張った、直角の動きをして歩き、停止します。
ですがマルコム演じるアレックスは、タタン、とリズムを取りながら停止していました。
この動きが踊っているようで、印象に残っています。
彼が本心から反省しているのではないことも見て取れました。
こちらの目を惹きつける動きが随所に見られてます。
世界観も前衛的
この映画では、登場人物や家の造形も、中々すごかったです。
上手く言えないのですが、前衛的と言いますか、芸術的と言いますか。
髪を、彩度の高い紫色や黄色に染めている人が度々登場するので、見る度にぎょっとしてしまいます。ですが、その髪色について誰も何も言いません。
観ているこちらはびっくりしてしまうのに、当たり前の姿として人々に受け入れられているのです。
劇中の世界で生きる人たちと観ているこちらの間に生まれる感覚の差は心地良いものがありました
そこで暮らしているほとんどの人がそんな具合なので、そういう町なのか、と思いながら観ていました。
視聴後に調べたところ、映画の舞台が「近未来のロンドン」であったことがわかりました。
近未来……なるほど……
だから彼らにとってあの家の内装もあの服装も、みんな当たり前のものだったのか、と納得したものがあります。
おわりに
- 風刺の映画
- 独特なスラングが多用されている
- 内容を説明しづらい
- 一種の芸術がある
- 好き嫌いが極端に分かれるタイプ
二回目は、観られないことはないです。
あくまで私は、という話ではありますが、たぶん、観ようと思ったら観られる、と思います。
でも積極的に観たいとは思えない、そんな映画でした。
それでも何かあったら、二回目の視聴をしてしまうかもしれません。
一緒に視聴した夫には、「私がまたこの映画を観たいと言い出したら一回止めてくれ」とお願いしておきました
数年後に観直したら、感じるものが変わるのかもしれない。
変わってしまうのかもしれない。
変わってしまうことが怖い。
そんな映画でした。