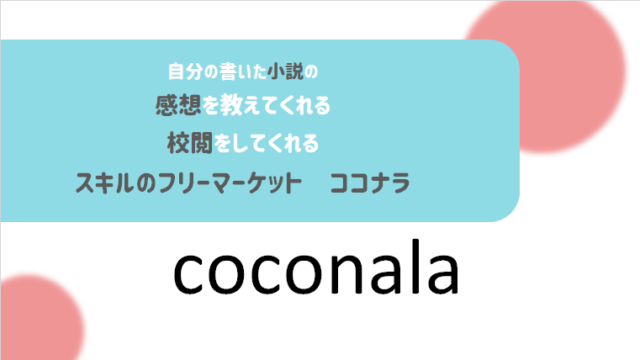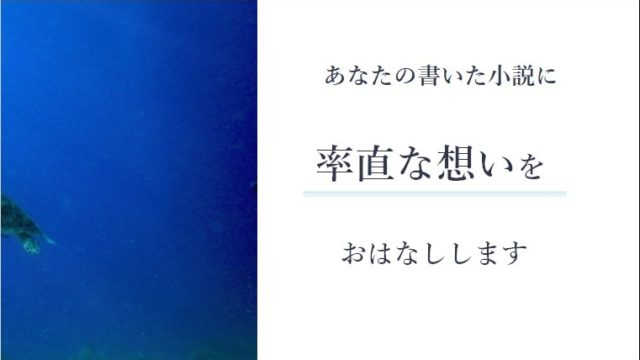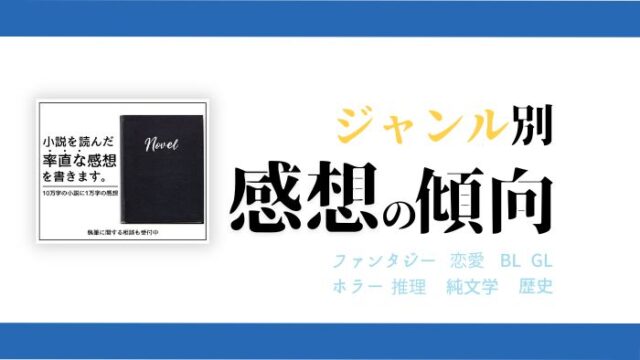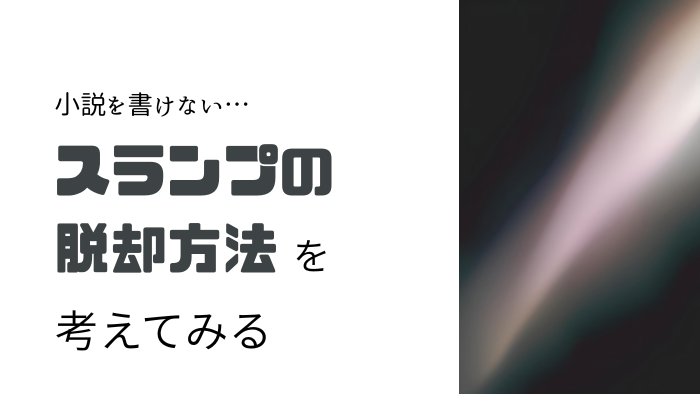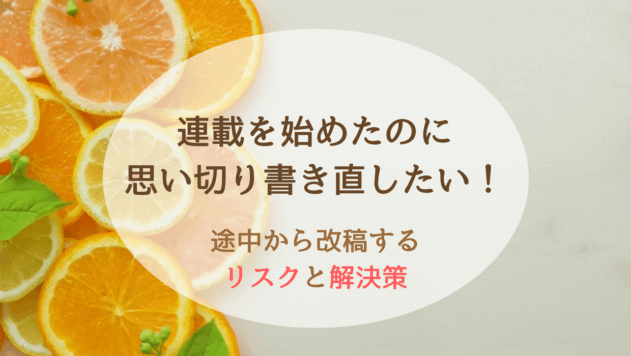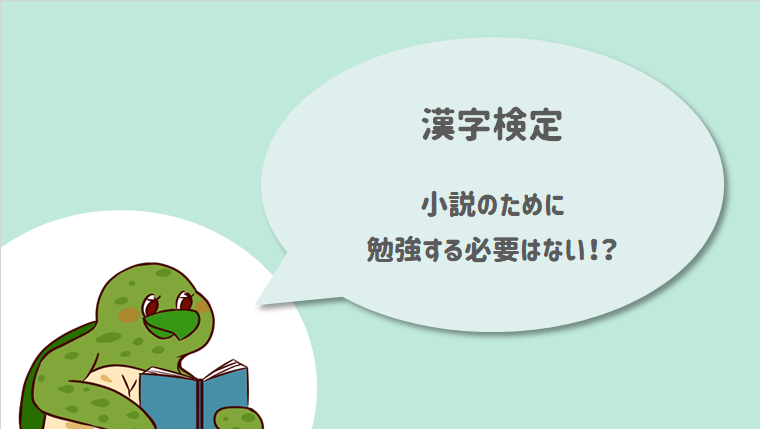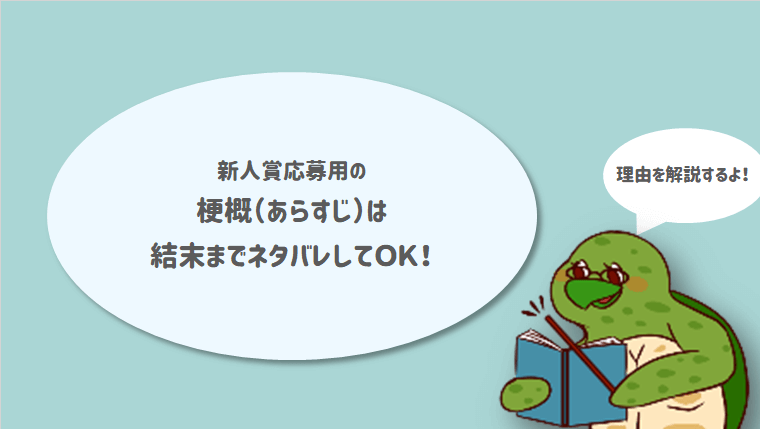小説の書き方|情景描写って何だろう?
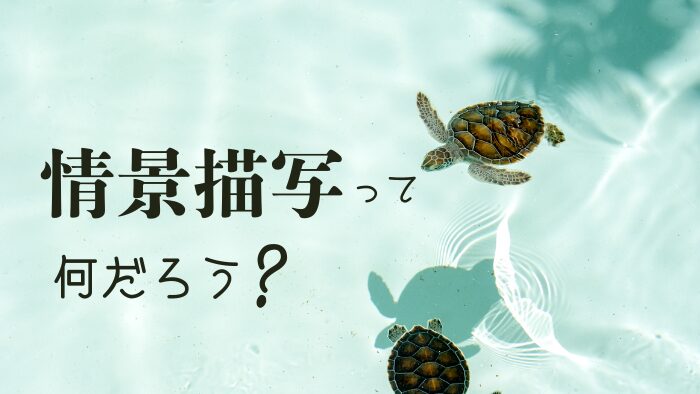
小説の書き方について調べていると「情景描写」という言葉が度々出てきます。
度々どころか頻繁に出てくるかも?
正解はこれだ、なんて断言することはできませんが、これかな、というのは分かったような気がするのでこちらにまとめます。
小説の書き方を学びながら、運営者が自分なりに記事にまとめていくブログ。
たまに好きな小説や映画の話もする。
「情景描写」の意味
そもそも「情景描写」ってどんな意味の言葉なんだろう?
まずは辞書で意味を調べてみます。
じょうけい【情景】
感興とけしき。
その人の目に映じたありさま。また、単に、ありさま。「ほほえましい―」「その時の―が目に浮かぶ」
びょうしゃ【描写】
描き写すこと。特に文芸・絵画・音楽などの芸術政策において、物の形体や事柄・感情などを客観的に表現すること。「心理―」
ちなみに「感興(かんきょう)」は「興味を感ずること。面白がること。また、その興味(引用 広辞苑第六版)」だそう。
小説に関して言うと、登場人物の目に映ったものや感じたものを、言語を用いて表現することが「情景描写」と言えそうです。
広辞苑で引いた意味から考えてみると、「描写」それ自体は難しいものではないのかもしれません。
- 物の形体を客観的に表現する
- ハナの目の前にボールがある。
- 感情を客観的に表現する
- ハナは笑って飛び跳ねた。
こういったものも「描写」の一種だと言えそうです。
さて、「感情を客観的に表現する」の例として「ハナは笑って飛び跳ねた」を挙げました。
これがどうして「感情を客観的に表現する」ことになるのか、少し詳しくお話しします。
行動から感情を推測させる
「感情を客観的に表現する」=「客観的な感情表現」のお話をする前に、主観的な感情表現について考えてみます。

「客観」の反対の、「主観」から考えていくと分かりやすいかな、と
客観的な感情表現と主観的な感情表現
- ハナは喜んでいる。
- ハナは悲しそうだ。
これらはどちらも「喜」と「哀」の感情をそのまま書いています。
「○○(人物)は、□□(感情)だ」
この形で書くと、主観的な感情表現となります。
- 人物を主語にする
- 感情を表す言葉をそのまま書く
といった条件を同時に満たすときに成立する、と言えるでしょうか。
主観的な感情表現の逆である、客観的な感情表現をしたいときは、これらの条件が片方でも成立しない文章を作ればいいわけです。
直接的な感情の言葉は使わずに表現する
初めの例に戻ります。
ハナは笑って飛び跳ねた。
この文は、人物(ハナ)を主語にしていますが、感情を表す言葉は書いていません。
でも、ハナの嬉しい、あるいは楽しいといった感情が伝わってきませんか?
読者という客観的な立場から、人物の感情を判断できるような一文になっているかと思われます。
この例文は「笑う」「飛び跳ねる」といった、行動だけでハナの感情を伝える試みをしています。
「笑う」「飛び跳ねる」といった行動をしている人は、どういう感情になっているかを読み手自身に判断してもらうためです。
これは読者としての私の経験によるものですが、感情を情報の一つとして伝えられるより、自分の中で生まれたものとして受けとめる形になっているものほうが、強く印象に残ることが多いです。
このため、この例文でも読み手自身に登場人物(ハナ)の感情を考えてもらう形にしました。
実際に間接的に感情を表現したいときも、その感情(目標)を抱くとき、人はどんな表情・動作をするだろう、とゴールから考えてみると良いかもしれません。
感情を間接的に伝えるための練習方法
ここでは感情を客観的に伝える書き方の練習方法をお話しします。
他にも良い方法はたくさんあると思うので、ここでお話しする方法は、「こういうやり方もあるんだなあ」くらいで捉えていただけると幸いです。
私が実践しているのはこちらの二つです。
- 練習方法① 表現を「縛る」
- 練習方法② ドラマや映画などの映像作品から感情表現を学ぶ
練習方法① 表現を「縛る」
小説の描写力や表現力を上げる方法としては「縛り」が良いかな、と考えています。
「これは書かない」と予め自分の中でルールを決めておくものです。
今回で言えば「登場人物の感情をそのまま書かない」となるでしょうか。
うっかり「ハナは悲しそうだった」などを書いてしまったときは、「悲しそうだった」を削除して、どうにか別の言葉でその状態を表現する、と頭を捻ります。
すごく頭を使いますし、普段の癖を矯正するようなものなので、すごく疲れます。
だからこそ、普段とは違った雰囲気の小説を書くことができますし、自分の表現力を鍛えることにも繋がります。
あとは、ドラマや映画を参考にするのも有効かなと。
練習方法② ドラマや映画などの映像作品から感情表現を学ぶ
小説は文章で表現されますが、ドラマや映画などは映像で表現されます。
小説は地の文(小説において、「」で括られた台詞以外の文章)で言葉を用いて感情を表現できますが、ドラマや映画ではできません。
「ハナは喜んでいる」とモノローグで伝えることもできますが、映像作品でこのようにするとギャグテイストになってしまう可能性もあります。
意図的にモノローグを活用している映像作品もありますが、ここではモノローグを使わずに感情を伝えてくる作品について考えていきます。
ドラマや映画を観ているとき、言葉で言われてはいないのに、観ているだけで登場人物の気持ちを感じることができることが多々あるかと思われます。
そういったとき私たちは、出演している俳優の表情や仕草、あるいは前後の場面の流れからその人の感情を読み取っています。
映像作品を観ながら、その映像から自分が何かしらの感情を受け取った・抱いたときは、なぜ自分がその感情を抱いたのかを掘り下げて考えてみます。
- 今はどういう場面なのか(誰が何をしているところなのか)
- 俳優はどんな表情をしていたのか(眉や目、口はどのような動き・形をしていたか)
- 俳優はどんな台詞を言っていたのか(直接的な感情表現の言葉がない代わりに、どういったことを言ったのか)
このようなことを考える習慣を身につけておくと、人物のどういう動きから、読み手がどういう感情を抱くのか、考えやすくなっていくかと思われます。
おわりに
情景描写というと、すごく難しいもののように感じるかもしれません。
ですがこの言葉の持つもの自体はそれほど難しいものではないんです。
小説を書いたことがあるなら、無意識だったとしても情景描写はやったことがあると思われます。
それでも極めようと思ったら難しいものですし、深めようと思ったら果てはないでしょう。
今回は、「ハナは笑って飛び跳ねた」を「喜」の感情を伝える例文としてお話ししました。
ですが、場面の構成や全体の流れによっては、同じ一文でも「哀」や「怒」といった、文章単体から想像されるものとは全く違った感情を伝えることができます。
場面構成と客観的な感情表現を上手く噛み合わせることができたら、より大きな感動を読み手に与えることができるかと思われます。
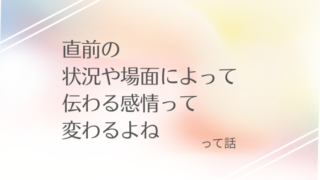
ちなみに、間接的に表現する、描写する、ということは、読み手が書き手の意図した通りに汲み取ってくれない可能性もあります。
全く意図していない方向に読み取られてしまったら物語として破綻してしまいます。
このため、自分なりに情景描写や間接的な感情表現に挑戦したら人に読んでもらい、狙い通りに感情が伝わったかを確認していく必要があります。
こういった点も踏まえた上で挑戦していただけると幸いです。